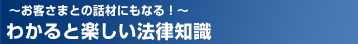|
債権の消滅時効は,永続した事実関係は真実に合致する可能性が高いことから,支払期限をこえて長期間が経過した場合には,弁済したという証拠がなくても,期間の経過だけを理由として債権の消滅を認めるものです。これによって,債務者は領収書等を保存しなくても安心できることになります。
例えば,ずっと昔に友人に返済した借金について,借用書が発見されたからと再請求されても,領収書なんて見つからないですよね。そんなとき,借用書の返済期限から10年以上が経過していれば,時効を援用して,債権は消滅したと主張できます。
この期間について,現行法は,権利を行使することができる時から10年間行使しないときは時効消滅することを原則としつつ,さまざまな例外を設けており,ルールが統一されていないため,分かりにくいと指摘されました。
このルールについて,いま法務省では改正を検討しています。法制審議会民法(債権関係)部会は,平成26年8月26日に開催された会議で民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案を承認しました(ただし,定型約款の部分は継続審議)。以下では,この案のことを「改正案」と言います。実際の法案になる時期は未定ですが,早ければ平成27年の通常国会に提出されることもあり得ます。
今回は,それを先取りして,新しい議論を御紹介します。
改正案では,職業別の短期消滅時効等(民法第170条から第174条まで)を削除し,また,債権の消滅時効における原則的な時効期間と起算点について以下のように改めることが提案されています。
民法第166条第1項※1及び第167条第1項※2の債権に関する規律を次のように改めるものとする。
債権は,次に掲げる場合のいずれかに該当するときは,時効によって消滅する。
(1) 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
(2) 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
(注)この改正に伴い,商法第522条※3を削除するものとする。
このうち,(2)の「権利を行使することができる時から10年」の消滅時効は,民法第166条第1項・第167条第1項による規律と同じです。ここにいう「権利を行使することができる時」は,権利を行使するための法律上の障害がなく,かつ,権利の性質上,その権利行使を現実に期待することができる時であると解されています(最判平成8・3・5民集50巻3号383頁)。
| ※1:民法第166条第1項…… |
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 |
| ※2:民法第167条第1項…… |
債権は、10年間行使しないときは、消滅する。 |
| ※3:商法第522条 ………… |
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。 |
|
|