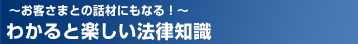|
保証人とは,主たる債務者(例えば借金をした人)が弁済できなかったときに,代わって弁済するという約束をした人のことです。銀行から融資を受ける場面を想定すると,主たる債務者はお金を借りて利益を得ていた人ですから,弁済しなければならないのは当然ですよね。これに対して,保証人は,ただ契約しただけで(お金をもらっていないのに)弁済義務を負う立場ですから,本来は慎重に考えなければいけません。
ところが,兄弟姉妹などの信頼関係のある人から「絶対に迷惑はかけない。協力してください」などと頼まれると断りにくいですよね。そのため,十分に危険性を考えることなく,安易に保証人になってしまう人が少なくありません。それでも,主たる債務者がきちんと弁済しているときは問題にならないのですが,多額の弁済を求められ,自宅を売却せざるを得なくなるなど,普通に生活できないところまで追い込まれてしまう事例もあります。
現在でも,保証契約の特殊性に応じて,契約書面でしなければ効力を生じないとされており(民法446条),特に危険性が高い貸金等根保証契約※では一定の事項を定めないと効力を生じないとされています(民法465条の2)。しかし,これでもまだ,保証人を十分には保護できていないという意見が有力です。
そのため法務省では,保証人を保護するための方策を拡充することを検討しています。法制審議会民法(債権関係)部会は,平成26年8月26日に開催された会議で要綱仮案を承認しました(ただし,定型約款の部分は継続審議)。以下では,この案のことを「改正案」と言います。実際の法案になる時期は未定ですが,早ければ今年の通常国会に提出されることもあり得ます。
今回は,従業員10名程度の株式会社の社長をしている弟から頼まれて,お兄さんが,銀行から5000万円の融資を受けるときに保証人になろうとしている事例をもとに,新しい議論を御紹介します。
| ※ |
貸金等根保証契約とは,一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)であって,その債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(貸金等債務)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く)のことです。 |
|
|