| > ���T�̃g�s�b�N�X > No.2447 |
| �@�l�̎����ŗ������Ƃ����ی���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�� �@�l�ւ̒�ẮA�����ŗ����l�������ی����z��
�@�l���ی�����������ꍇ�́A�G�����i�ی����ϗ����܂��͑O���ی���������ꍇ�́A�������T���������z�j�Ƃ��ĉېőΏۂƂȂ�A�@�l�ł̂ق��ɖ@�l�Z���ł�@�l���Ɛœ����ېł����B���̂��߁A�@�l�ɑ��Ē�Ă��s���ۂɂ́A�@�l�ɑ��邷�ׂẲېł̗v�f���������������ŗ������ƂɁA�ېŕ��f�����邽�߂̕K�v�{�����u100%���i100%�|�����ŗ��j�v�ɂ���ĎZ�o���A�u�K�v�ȕۏ���z�~�K�v�{���v�ɂĎZ�o���ꂽ�ی����z���Ă���K�v������B
�� �����ŗ��Ƃ͉���
���������@�l�̎����ŗ��Ƃ́A�@�l�ɑ��ĉېł����ŋ��A�܂�A�@�l�ŁA�@�l�Z���Łi�@�l�Ŋ��j�A�@�l���Ɛł���ђn���@�l���ʐł����ׂĉ��������ېŏ����ɑ���ŗ��������B�������A�e�Ŗڂ̉ېőΏۂ̈Ⴂ�����邽�߂ɒP���ɐŗ��̍��v�Ƃ͂Ȃ炸�A����ɂ͖@�l���Ɛł���ђn���@�l���ʐł������Z������邱�Ƃ��l�����Čv�Z����K�v������B��̓I�ɂ́A���̂悤�Ȍv�Z���ɂ��Ă͂߂ĎZ�o����B
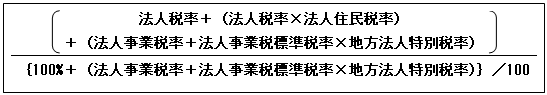 �@�l�ŗ���25.5���A �@�l�Z���ŗ��i�s���{�����Ł{�s�������Łj��17.3���i�W���ŗ��j�A �@�l���Ɛł̐ŗ���5.3���i���ʖ@�l�̍ō��ŗ��ł̕W���ŗ��j�A �n���@�l���ʐŗ���81%�i�O�`�W���ېŖ@�l�ȊO�̏ꍇ�̐ŗ��j�̏ꍇ�A �P�����v�����u�\�ʐŗ��v�� 25.5%�{�i25.5%�~0.173�j�{�i5.3%�{5.3%�~0.81�j��39.50%�ƂȂ邪�A �u�����ŗ��v�́A�����Z�������i5.3%�{5.3%�~0.81�j�����l�����āA 39.50%���i�P�{0.096�j��36.04���ƂȂ�B ���ۂ̎����ŗ��́A�@�l�̎�ނ⏊�����z�A�@�l�̏��ݒn�ɂ��n���ŗ��̈Ⴂ�ɂ���ĕω����A�܂��A�@�l���Ɛł�n�����ʖ@�l�ł͑O�N�x���������Z������邽�߁A��L�̌v�Z�l�͈ꉞ�̖ڈ��Ƃ��ė������Ă������ƂƂȂ�B �� �@�l�ŗ��̉����ƕ������ʖ@�l�ł̑n�݂ɂ��e��
����23�N�x�Ő������ł́A����24�N4��1���ȍ~�ɊJ�n���鎖�ƔN�x�̖@�l�ŗ����A���ʖ@�l�̏ꍇ30%����25.5%�Ɍy����������A�������ʖ@�l�ł����Ԍ���őn�݂���A�@�l�ł̊�@�l�Ŋz���ېŕW���Ƃ���10%�̐ŗ��ʼnېł���邱�ƂƂȂ����B�������ʖ@�l�ŗ������������@�l�ŗ��́A25.5%�~�i1�{0.1�j��28.05���ƂȂ�i�����@�l���ʐł́A����24�N4�����畽��27�N3���܂ł̊��ԓ��ɍŏ��ɊJ�n���鎖�ƔN�x�̊J�n������Ȍ�3�N���o�߂�����܂ł̊��ԓ��̓��������鎖�ƔN�x�ɂ����ĉېł����j�B
���̌��ʁA�������ʖ@�l�ł��������������ŗ��͎��̂悤�ɂȂ�B���̂��߁A�ی���Ă̍ۂɍl�����ׂ��@�l�ł����Z�����ی����z���Z�o���邽�߂̕K�v�{�����ω����邱�ƂƂȂ�B
���ɐň�����łP���~���K�v�ł���A����24�N4���ȍ~�J�n�̎��ƔN�x�ɂ����ẮA1���~�~1.63����1��6,300���~�̕ی����z�̐ݒ肪�K�v�ƂȂ�B
����23�N�x�Ő������ɂ���Ė@�l�ŗ����i�K�I�Ɍy������邱�Ƃɔ����A�����ŗ���������A�K�v�{�����������邱�ƂɂȂ�B�@�l�ɑ����ƕۏᏀ�������Ƃ��ĕی����Ă���ۂ́A�����ŗ��ɑ������ی����z�̒�Ă��K�{�ł��邪�A������@�l�ʼn����̓����Ɋւ�����@�l�̂��q�l�ɂ��͂����邱�ƂŁA��Ă̐���Ƃ��Ċ��p����������K���ł���B
���{�e�̓��e�́A2012�N6��1�����݂̐Ő��ɂ��܂��B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012.06.25 |
|