| > 今週のトピックス > No.2570 |
| 「物価上昇率2%」実現で景気は回復するか | |||||||||||||
|
1月22日、政府と日銀の政策連携が成立し、共同声明が発表された。政府・日銀が一体となり、デフレから脱却するため、消費者物価の前年比上昇率(物価上昇率)2%の早期実現を目指すことになった。物価上昇率2%が経済にどのような影響があるのか、私たちの生活はどのようになるのかを考えてみたい。
1)過去の推移から見ると、かなり高い目標
政府は物価目標を明確にすることで、金融緩和を推進し、物価上昇率を高める効果を期待しているが、日本の過去20年の消費者物価の前年比推移(図表参照)や現在の物価動向から判断するとかなり高い目標といえるだろう。 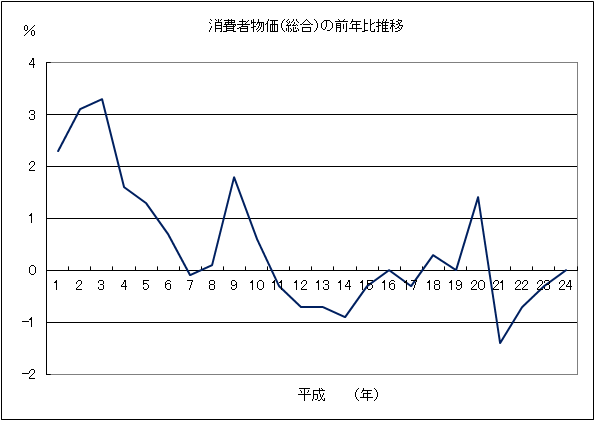
2)債券価格は急落、金利は大きく上昇
もし、物価上昇率2%が現実的になった場合には、金利が大きく上昇する可能性が高い。なぜなら、物価が上昇すると投資家は債券を保有するより、モノに投資したほうが投資効果が大きいと考え、債券を売却しモノを購入するため、債券価格は急落し金利は上昇することになる。
3)スタグフレーションが起きる可能性も
金融広報中央委員会の調査によると、2012年金融資産残高の増減では貯蓄が増えたと答えた人の割合は19.2%、減ったと答えた人は40.1%となっている。また、年間手取り収入(税引き後、平均)は、2000年に557万円だったが2012年には489万円と約70万円も下がっている。一般消費者は給料が減った分を、貯蓄を取り崩して生活している人が多いようだ。 このような経済状態で物価が上昇した場合、不景気下の物価高(スタグフレーション)が起きる可能性もある。また、金利が上昇すれば住宅ローン金利も上昇し、変動金利で借りている人は返済額も増える。給料は上がらず物価が上昇し、住宅ローンの返済も増え、家計を圧迫し破綻することも考えられる。物価上昇は重要な目標であるが、それだけでは経済成長はない。一般消費者の収入や貯蓄を増やし、懐が暖かくなったことでモノを買うように仕向けることが物価上昇につながる。
4)民間企業には追い風だが、金融政策だけでは難しい!?
日銀が金融機関から大量の国債を購入することで、日銀の貨幣が市場に放出されて長期金利が低下する。その結果、民間企業が資金調達を容易に行うことが可能になり、景気が回復することを期待している。デフレ脱却には、金融緩和は重要であるが、上記1)2)3)から、金融政策だけではデフレを脱却することは難しそうだ。
|
|||||||||||||
| 2013.02.07 |
|