| > 今週のトピックス > No.2914 |
| 財務省が後発医薬品使用を強力にうながす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● 後発医薬品の使用促進目標が「遅すぎ、低すぎ」と厳しく批判
社会保障の管轄省庁といえば厚生労働省だが、こと財政運営が絡んでくると財務省からの圧力が強くなる。10月8日に開催された財務省の財政制度等審議会(財政制度分科会)の議論でも、社会保障を担う行政に大きな影響を与える提言が発せられている。
介護保険分野については、来年度の介護報酬改定議論に横ヤリを入れるかのように、全体の改定率をマイナス6%程度とする旨が提言された。介護事業者の収支差率が改善していることを根拠とした数字だが、仮にこの数字の通りになると、介護保険制度創設以来の大幅なマイナス改定となる。案の定、業界団体からは強い反発が続々と上がっている。 では、医療分野ではどうか。この部分でもさまざまな提言がなされているが、中でも「現在の目標は遅すぎ、低すぎ」という文言で厚労行政が手厳しい批判を受けたテーマがある。それが、医療費引き下げに大きな効果をもたらすとされる「後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進」だ。周知の通り、新薬の特許期間が切れてから別メーカーによって製造された医薬品のことで、開発費用が軽減されるため低価格で販売することができる。 厚労省は平成25年4月に、後発医薬品シェアの目標※として、平成30年度までに60%以上という目標を掲げた。この目標設定に対し、財政制度等審議会から出てきたのが、先の「遅すぎ、低すぎ」批判だ。批判の論拠は、この60%以上という数値が従来の政府目標(68%)より低位であるという点が一つ。そして、「60%」という数字を参考にしたフランスでは、平成24年時点ですでに70%以上を達成した点などをあげている。 ● 先発医薬品を選択した場合、後発医薬品を上回る分は患者負担という案も
そのうえで財務省が注目しているのが、厚労省が60%目標を掲げた際に策定した「後発医薬品の使用促進のためのロードマップ」だ。このロードマップでは、医薬品の業界団体や保険者、医療機関などの取り組みを示しているが、財務省が問題視しているのが「保険者がその機能を発揮して被保険者(患者)に使用をうながす」しくみの弱さである。ちなみに、現状の取り組みとしては、「保険者による患者への差額通知、後発医薬品希望シール(後発医薬品を希望する旨を示すシールで、健康保険証やお薬手帳などに貼って使用する)等の普及」があげられている。
これに対し、財務省側が求めているのは、被保険者の保険料や医療費自己負担にかかるインセンティブを強化するしくみだ。保険料でいえば、たとえば国保への財政支援を強化するにあたり、被保険者の後発医薬品の使用割合を配分指標の一つとするというもの。これにより、後発医薬品の使用が進んだ保険者の保険料が軽減されるしくみを求めている。 患者の医療費負担については、保険給付額を後発医薬品に基づいて設定するというもの。先発医薬品の取引価格は当然それを上回ることになるが、上回った部分はすべて患者負担となる(参照価格制度・下図参照)。類似の制度は、すでにドイツやフランスでも導入されている。 図:参照価格制度のイメージ
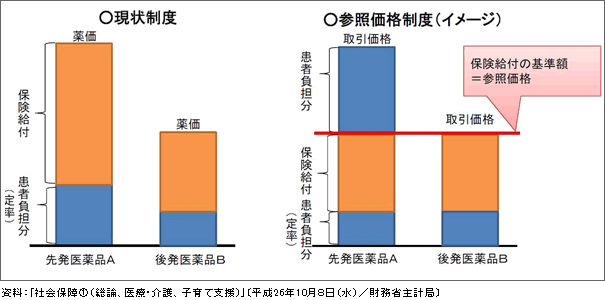
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014.10.30 |
|