| > 社会保障制度の基礎知識 > 介護編 |
| 要介護(要支援)認定 | |||||||||||||||||||||||
|
●認定調査
要介護認定申請をすると、申請者にどの程度の介護が必要なのかという調査が行われます。この認定調査は、申請者宅(申請者が施設や病院などの場合はその場所)に、調査員である自治体の職員あるいは市町村が委託した事業所の調査員等が訪問し、申請者およびその家族などからの聞き取りにより実施されます。
調査は認定調査票をもとに、申請者本人に質問をし、その回答を調査票に書き込む形式で進められます。調査票は本人の心身状態を調査するための「基本調査項目」および「概況調査」、「特記事項」から成り立ちます。 【認定調査の質問分野とその内容】
これらの質問は選択肢をチェックしていく形式で進められますが、それぞれの項目の中で特に考慮したい内容がある場合は「特記事項」として記入されます。
また、調査票には、本人や家族の連絡先、すでに介護サービスを受けている人はその種類など、基本的な概況データを記入する「概況調査」欄が設けられています。調査対象者本人の主訴や家族の状況、居住環境などに関して特に考慮すべき場合についても記入欄が設けられています。 ●コンピュータによる1次判定
以上の認定調査票への記入に基づいて、要介護認定申請者にはどれくらいの介護が必要であるかが判定されることとなります。
まず、基本調査項目の回答がコンピュータ処理され、要介護認定等基準時間が算出されます。下記の8分野の介護に要する要介護認定等基準時間の合計が「25分以上32分未満」の場合などが要支援1、「32分以上50分未満」を要支援2または要介護1とし、以後20分刻みで要介護度が上がり、110分以上の場合は最重度の介護を要する要介護5とされます。この結果を1次判定といいます。 【8つの生活場面ごとの介助時間】
※BPSDとは認知症に伴う行動・心理症状のこと。
(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia の略)
●介護認定審査会による2次判定
次に各市区町村ごとに設けられた介護認定審査会において、1次判定の結果をもとに訪問調査の特記事項、主治医の意見書等の内容を加味し、要介護状態区分ごとに示された複数の状態像の例をもとにして審査判定を行います。これを2次判定といいます。介護認定審査会は通常、保健・医療・福祉の学識経験者5名程度で構成されています。
以上、1次・2次の判定を経て、最終的にその人の要介護度が決定します。 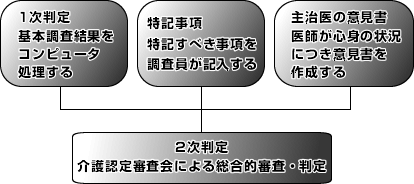 ●市区町村による認定の通知
市区町村は審査会の決定を受け、要介護認定申請者に結果を通知します。要介護度は、介護の必要度に合わせて1から5、さらに要介護1より軽いレベルの要支援1および2という全部で7段階となります。
また要介護、要支援に該当しない人の中で、「要介護・要支援になるおそれのある者」と判定された場合は、地域包括支援センターを通じて地域支援事業としての転倒骨折予防教室や栄養指導などを受けることができます。 なお、判定に不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から原則60日以内に、都道府県が運営する介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。 |
| 2025.04.01 保坂 |
|