| > 社会保障制度の基礎知識 > 労災・雇用編 |
| 労災保険 通勤災害とは | |||||||||||||
|
●通勤災害の認定
この通勤の定義が具体的にどういう場合を指すのか、一つずつ確認していきましょう。 まず、「就業に関し」というのは、就業との関連性が必要であるという意味です。つまり、通勤時刻と始業時刻・終業時刻との関連性が必要なのです。なお、遅刻や早退などの場合は就業との関連性が認められています。 次に「住居」ですが、これは労働者が現に居住している建物をいいます。入院中の家族を看護するために宿泊している病院は、住居として認められます。また、単身赴任者の単身赴任先と家族等の居住する自宅の間や、複数の勤務先を持つ場合の事業所間も通勤災害の対象です。 「就業の場所」は労働者が仕事を始める場所や仕事を終える場所とされ、営業先からの直帰なども含まれます。 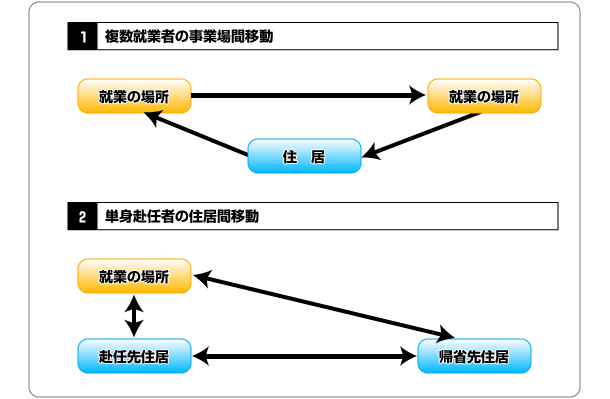 また、「合理的な経路および方法」は、社会通念上、誰もが当然であると認める経路と方法を指します。つまり、通常、通勤に利用する公共交通機関や車、バイク、自転車、徒歩などをいいます。
「業務の性質を有するもの」は、業務災害の対象となるため、通勤災害からは除くという主旨です。 ●逸脱・中断
また、通勤の途中で往復の経路を逸脱したり、中断したときには、逸脱または中断した後の往復は通勤にはなりません。つまり、会社帰りに私的行為を行う場合は、通勤に含まれないということです。
ただし、すべての逸脱・中断が対象外では厳しすぎますので、「日常生活上必要な行為を最小限度で行う場合」については、逸脱または中断した場合であっても、その後通常の経路に戻った時点から通勤と認められます。(図参照) 【中断・逸脱したときの通勤の例】
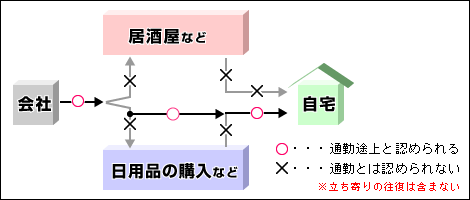 日常生活上、必要な行為の例としては、
などが該当します。
これらの行為を通勤途中にする場合、その行為中は対象外ですが、行為が終わった後に通常の経路に戻った時点から通勤の対象になります。例えば、帰途でスーパーにおいて惣菜を購入している最中にスーパー内でけがをしたときは対象外です。しかし、買い物を終えて通勤経路に戻り、その道路上でケガをしたというようなときには通勤災害の対象になり得るということです。
ただし、買い物が終わってから長時間雑談などに興じていると、その後は通勤災害の対象にならなくなってしまうので注意が必要です。 一方、通達で日常生活上必要な行為と認められていないものには、
などが挙げられます。これらの私的行為を行った場合には、私的行為の後に通勤経路に戻ったとしても、その逸脱または中断の間とその後の往復は通勤にはなりません。
なお、通勤災害かどうかの認定・申請は労働基準監督署において行われます。
交通事故の場合も労災保険を使えますが、自賠責保険を使えるときには、自賠責保険が優先されます。自賠責保険による治療などの額を超えるときには、金額が超えた時点から労災保険の給付を受けることができます。 |
| 2025.04.01 保坂 |
|