| > 社会保障制度の基礎知識 > 労災・雇用編 |
| 雇用保険 求職者給付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●求職者給付の受給要件
雇用保険の求職者給付とは、雇用保険に加入していた方が失業した場合に、再就職するまでの一定期間の生活の安定を図るために支給される給付金です。
一般的に「失業手当」とか「失業保険」と呼ばれますが、正確には「雇用保険の求職者給付」です。単に失業状態に対して給付するのではなく、あくまでも、仕事を探している失業者の生活をサポートするという主旨からです。その中でも内容に応じて、給付金の項目が細かく区分されています。最も一般的な失業者への給付は「基本手当」です。 求職者給付を受けるには、次の2つの要件を満たす必要があります。
転職期間が1年以内で雇用保険を受給していなければ、前の会社での被保険者期間を通算することができます。
*病気やけが、妊娠・出産・育児などですぐに働けないときなどは対象外ですが、受給期間延長制度があります。
●受給手順
会社では、社員を雇用した際に雇用保険の資格取得を届出ます。そして、被保険者が退職・死亡、労働条件の変更などにより被保険者でなくなったときには、その事実のあった日(退職日など)の翌日から10日以内に、ハローワークへ資格喪失届を提出します。
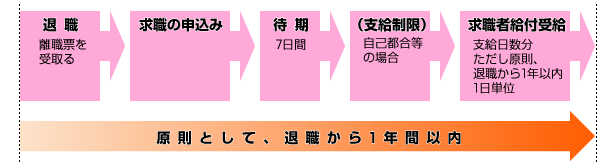 離職して求職者給付を受けたい場合、退職者は会社から「離職票」を受け取ります。この「離職票」は、過去半年〜1年の賃金等を証明するものです。離職票のほかに必要な書類として、雇用保険被保険者証、印鑑、住民票または運転免許証、写真1枚、本人名義の普通預金通帳などを用意して、本人住所地を管轄するハローワークへ求職の申込みをします。
求職の申込みから失業状態の通算7日間つまり「待期期間」は何も給付がありません。会社都合による退職であれば、待期期間7日を経過後すぐに支給対象期間が始まります。自己都合による退職の場合は「待期期間7日+給付制限期間原則1ヵ月(5年間のうち2回以上の自己都合離職等がある場合は3カ月)」があり、その間は失業給付を受けることができません。 原則4週間ごとハローワークの指定日に出頭することで「失業の認定」を受けます。その認定された期間、つまり過去の求職期間に足して求職者給付が支給されるのです。 受給期間は退職翌日から1年間ですが、病気やけが、妊娠・出産・育児などの理由によりすぐに働けないときには、失業給付の受給期間を延長することができます。 ●給付額
1日あたりの給付金額「基本手当日額」は、退職直前6カ月の給与の合計を180で割って算出した「賃金日額」の5割から8割です。60歳から64歳の場合は4.5割から8割です。賃金が低いほど高い給付率で計算されます。この基本手当日額は、退職時の年齢によって異なります。
また、年齢区分ごとに基本手当日額の上限額が決まっています。計算式の基準や上限額は、統計に基づき、毎年8月に改定されます。 ●支給期間
基本手当の給付日数は、雇用保険の加入年数によって決まっています。
倒産・解雇など本人の意思とは無関係に失業状態となった人については、自己都合で退職した人よりも多く給付されるようになっています。
例えば、30歳以上45歳未満で被保険者期間10年以上20年未満の人が、自己都合退職のときの給付日数は120日です。
なお、障害者等の就職困難者に該当する場合はより手厚く、表よりも給付日数が多くなっています。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.04.01 保坂 |
|