| > 今週のトピックス > No.2377 |
| 金融庁が法改正検討、投資信託の「配当し過ぎ」に歯止め | |||||||||
|
金融庁は、リスクが高い投資信託を高齢者や経験の浅い投資家が購入を控えるように、投資信託法を見直すこととした。毎月支払われる分配金の原資を運用益に限定することや、デリバティブ(金融派生商品)の利用を制限する措置を検討する。
1.毎月分配型投資信託の人気
「毎月分配型投資信託」とは、毎月分配金が支払われる投資信託をいう。
毎月分配を行う投資信託の残高は2011年5月末に31兆円を超えた。これは、2008年のリーマンショック前の水準まで回復してきたことになる。 同ファンドは50代から70代の投資家から人気を集めており、公的年金の不足分を補う目的で購入している投資家も多い。株式市場の低迷や為替の円高等の要因で資産運用が困難となっているなかでも、ハイ・イールド債などを組み込んだ投資信託は毎月多くの分配金がもらえるため、人気を呼んでいる。 2.分配金のしくみと誤認
投資信託では、基本的には運用益を分配金として投資家に支払う(普通分配金)ことになっているが、運用益が出なくても元本を取り崩して分配金(特別分配金)を支払うファンドも増えているのが現状だ。毎月分配型投資信託の購入層の中心は投資経験の浅い投資家であるため、毎月、運用益から分配金が支払われていると思っている方が多い。しかし実際は、運用益が出ているかを問わず、毎月分配金が支払われる。そのため、いざ売却するときになって元本が大きく下がっていることに驚き、「こんなはずではなかった」などと途方にくれることになる。実際、普通分配金、特別分配金の違いを理解されていなかった方から、「このファンドは分配金が多いが、分配金を支払っている会社は大丈夫なのか」とたずねられたこともある。このような誤認を是正するために、金融庁は分配型投資信託の規制に動いたようだ。
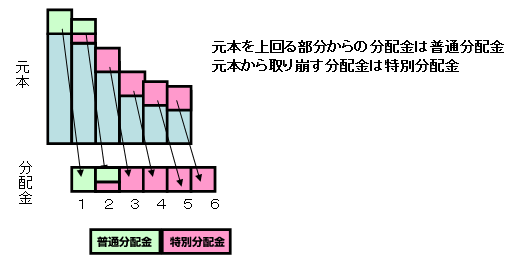 3.規制を検討
これまでも、運用成績が悪化しても、従来の高い分配金水準を維持する商品は多かった。分配金を下げれば販売にマイナスになると考える販売会社が多く、分配金の支給額を決める運用会社も分配金を減らしたり、無分配とすることには動きにくかった。
そこで金融庁は個人投資家を保護するため、1月27日の金融審議会で、毎月分配型の配当原資を運用益に限定する規制を検討することとなった。 米国では原則、金利収入と値上がり益を原資に分配しているため、運用が悪化した場合でも高い分配金を分配することはない。日本も早く高齢者が安心して投資できる環境を整備する必要があるだろう。
|
| 2012.02.13 |
|