| > 今週のトピックス > No.2381 |
| 職場のパワハラ定義 明確化へ〜厚生労働省〜 | |||||||||
|
● これまでなかった「パワハラ」の定義が明確に
厚生労働省のワーキング・グループは、1月30日、パワーハラスメントの定義や、企業が取り組むべき対策などを盛り込んだ報告書を取りまとめ、公表した。厚生労働省ではこの報告書を基に、3月までに問題解決のための具体的な方策をまとめる予定となっている。これまで、明確なパワーハラスメントの定義というものはなかったが、今回の報告書で具体的に定められたことは大いに意義があるといえる。
● パワハラの6つの行為類型
今回の報告書の中では、「職場のパワーハラスメント」を「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義した。
さらに職場のパワーハラスメントの行為類型を以下のとおり6つに分けているが、職場のパワーハラスメントのすべてを網羅するものではないことに留意しておく必要はある。 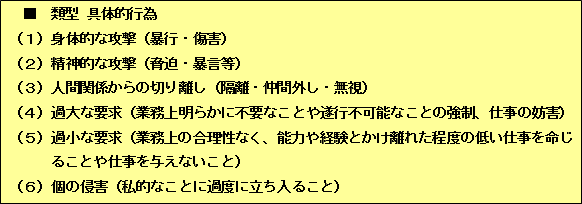 ● 今後のパワハラ予防策
報告書の中では、今後のパワーハラスメントを予防するのに必要なこととして、組織のトップからのメッセージの重要性を挙げている。組織のトップが職場からパワハラをなくすことを明確に示すことはとても大切である。例えば、朝礼でのスピーチや全体会議などでの発表が想定されるが、そのほか社内報への掲載なども効果があるだろう。
また、社内でルールを決めることも、とても重要である。就業規則にパワーハラスメントに関連する規定を設けるのはもちろんのこと、予防解決のガイドラインや指針を各企業が作成することも強く勧めたい。 パワーハラスメント対策といえば、研修は欠かすことができない。社員の階層別にきめ細かく対応した研修を継続的に実行していくことで、ある程度の予防につながる。研修を受けられない人へのフォロー体制や、定期的にセルフチェックなどを行う仕組みをつくり、継続的に注意喚起することも忘れないようにしたい。 参考 厚生労働省 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd.html
|
| 2012.02.20 |
|