| > 今週のトピックス > No.411 |
| 変わる住宅ローンとこれからの住宅取得 | |
|
○住宅金融公庫融資の制度改正
小泉内閣による「政府系金融機関の整理縮小」という方針を受け、住宅金融公庫も将来的に廃止の方向が打ち出された。その前段階として制度の縮小が本年度から始まっている。これまでの制度では、収入など所定の要件を満たせば、住宅金融公庫から物件価格の100%の融資を受けることが可能だった。しかし、今年度からは物件価格の最大80%までしか融資を受けられないことになった。
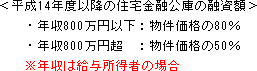 ○住宅金融公庫に代わる民間金融機関のローンの開発
これは昨年より20万人少なく、21年連続して減少し続けている。男女別で見てみると、男児が931万人、女児が886万人と男児が45万人多くなっている。1,817万人のうち、未就学の乳幼児(0〜5歳)は709万人、小学生(6〜11歳)は721万人、中学生が387万人で、年齢3階級別に見ると年齢が低いほど少なくなっていることが分かる(図1参照)。
○公庫廃止前の駆け込み取得が有効か?
さて、これからマイホームを取得しようと考えている人たちは、公庫廃止というニュースに、大きな不安をかき立てられたのではないだろうか。住宅金融公庫の住宅ローンは長年住宅ローンの代名詞であり、民間金融機関にはない有利な商品性を持っているというのが常識であった。しかしながら、前述の通り、必ずしもこの常識は当てはまらなくなってきており、あまり慌てる必要はないと思われる。むしろこれからの時代にあった住宅取得計画をじっくりと立てることが、肝要ではないだろうか。
これまで、住宅金融公庫で物件価格の100%を借りられたこと自体が異常であり、今後は十分な頭金を準備し、収入が減少した場合でも返済が可能なように、無理のない返済計画を立てる必要があるだろう。右肩上がりの収入増加が望めないどころか、収入ダウンのリスクまで考慮しなければならなくなった今日にあっては、「どのような条件でいくらまで借りられるか」ではなく、「いくらなら少々の収入ダウンがあっても返せるか」という視点が重要となってこよう。
|
| 2002.05.14 |
|