| > 今週のトピックス > No.586 |
| ユーロ経済の不安要因とユーロ投資への影響 | |||||||||
|
ユーロは、通貨流通から2年余りで今やドルと双璧をなす通貨となった感がある。特に、2002年下期からは、ユーロが円・ドルに対し高値となるいわゆるユーロ独歩高の状態が続いている。この結果、個人投資家の間でユーロ建て金融商品が急速に広がっているとたびたび報道でも取り上げられ、すでにご存じの方も多いのではないだろうか。ユーロ独歩高の傾向は、毎月月初のドル・ユーロの対円のTTM*1をまとめた下図を見れば一目瞭然であろう。
【ユーロ・ドルのTTM(2002年1月〜2003年3月)】
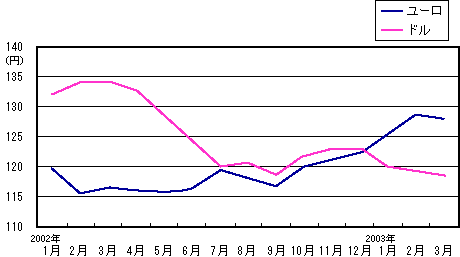 2002年のユーロ独歩高の主な要因は、
などが考えられる。さらに言えば、ユーロ高の要因は、(1)〜(3)のような「ドル安に起因するもの」と、(4)のような「ユーロ経済に起因するもの」が入り混じって、上記のグラフのようなユーロ独歩高を招いているということである。
そこで、今後もユーロ独歩高となるかに注目が集まるところであるが、その可能性は低いと思われる。なぜなら、3月6日に、欧州中央銀行(ECB)は、政策金利を0.25%引き下げ、年2.5%(過去最低水準)とした。これは、ユーロ経済自体がかなり悪化してきていることを表しており、これまでのユーロ高を支えてきた(4)の要因にブレーキをかけることになる。
一方、(1)〜(3)はイラク問題に起因したものが多い。言い換えればイラク問題さえ解決すれば、(1)〜(3)の要因は払拭され、ドル高・ユーロ安へと転換する可能性があるということだ。
さらにユーロ経済にとっての大きな懸念材料として、米国国内でのドイツ・フランス製品の不買運動が挙げられる。これはイラク問題におけるドイツ・フランスと米国の対立に起因するものであることは言うまでもない。もしこのような運動が大規模に展開され、ドル高・ユーロ安へと向かい始めれば、現在の日本がそうであるように、輸出産業で自国経済の立て直しを図るというドイツ・フランスの経済政策に大きな支障をきたし、さらにユーロ経済全体にとって深刻な悪影響を及ぼすだろう。
これにより、ユーロ経済での景気刺激策として残されるのは、過去最低水準とはいえ日・米に比べまだ高い欧州中央銀行(ECB)レートのさらなる引き下げだろう。
しかしこの結果、ユーロ経済が日本同様に長期低金利政策へ突入すれば、日本の個人投資家に急速に広がっているユーロ建て預金やユーロ建てMMFなどに深刻な影響を招くことになる。また、最近人気を集めている毎月分配型投信においても、分配金原資である債券のインカムゲインが長期では減少となる可能性もある。
順風満帆に見えたユーロ経済、そしてユーロ投資であるが、事態はことのほか深刻さを増しているようである。このように不透明な状況の中、個人投資家が外貨投資を始めるのであれば、資産運用の基本である分散投資に徹し、ドル・ユーロの通貨分散をぜひ心がけたい。
また、すでに外貨資産を保有している投資家においても、過度にユーロに偏ったポートフォリオを組んでいないかをチェックし、もしそうであれば、ドルの比率を若干上げるようなリバランスが必要な時期にさしかかっているのかもしれない。
*1 TTM(Telegraphic Transfer Middle rate)
外国為替取引の電信相場(TTR)で使われる略語で仲値のこと。外国為替取引は銀行間取引と対顧客取引の二つに大別され、TTMは対顧客向けの基準レート。
*2 FF(Federal Funds)レート
米国のFRS(連邦準備制度)の加盟銀行は、預金残高の一定割合を連邦準備銀行に預け入れることが義務付けられており、この資金が不足している時などに、余剰が出ている銀行より資金を借りる際の金利のこと。
注)本記載内容は参考情報の提供を目的としたもので、取引や投資戦略の勧誘および申し込みを行うものではありません。また情報の正確性や完全性は保証されていません。本記載の実績においては、過去の実績を表すものであり、必ずしも将来の実績を示唆するものではありません。
|
| 2003.03.18 |
|