| > 今週のトピックス > No.628 |
| 夫婦の老後に必要な収入月額は? | ||
|
●平均月額36.4万円で、自助努力により老後生活を賄う
生命保険文化センターは、5月15日に平成14年度「企業の福利厚生制度に関する調査」を発表した。前回は平成10年度に行われており、今回5年ぶりの調査になる。
図1は、老後を夫婦2人で暮らしていくために必要な収入月額について、従業員を対象に調べたもので、次のような結果になっている
【図1 夫婦の老後に必要な収入月額】
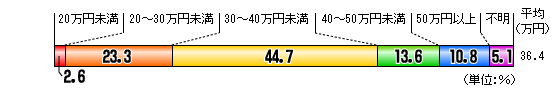 「30〜40万円未満」が44.7%と最も多く、次いで「20〜30万円未満」(23.3%)、「40〜50万円未満」(13.6%)と続き、平均36.4万円となっている。
生命保険文化センターの「平成13年度生活保障に関する調査」によると、夫婦2人の「ゆとりの老後生活費」は月額37.3万円となっており、前述の従業員などが必要とする夫婦の老後生活資金の目安とほぼ近い月額になっている。
今回の調査で興味深いのは、次の年齢別グラフだ。
【図2 年代別、夫婦の老後に必要な収入月額】
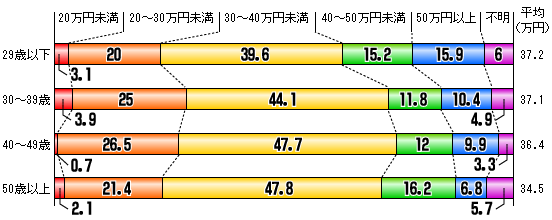 29歳以下では、「50万円以上」が15.9%と30歳以上のどの年齢層と比べても多くなっている。また、平均額においては29歳以下が37.2万円と最も高く、年齢が上がるにつれて、平均額が下がっている。
また、「老後の収入の内訳」では、老後に予定している収入として「公的年金」が50.6%、「労働による収入」(20.2%)、「退職一時金、企業年金」(15.5%)、「その他の金融資産」(9.8%)となっている。ここでも以下の年齢別グラフで見てみよう。
【図3 夫婦の収入の内訳】
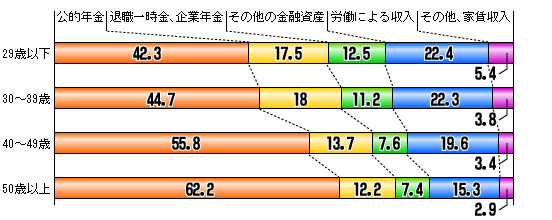
公的年金の支給開始年齢の引き上げや支給金額の引き下げなどから、公的年金に対する若者の先行き不安を反映してか、若い層ほど「公的年金」の割合が低く、その一方で「労働による収入」や「その他の金融資産」が高くなっている。
30〜39歳は、「退職一時金、企業年金」が18.0%と高く、企業型確定拠出年金などに対する期待や興味をうかがうことができ、「その他の金融資産」(11.2%)と合わせると約3割になる。
つまり、若い層ほど、老後に必要な収入を公的年金に依存するのではなく、老後も働き続けて収入を得て、自助努力による資産形成を考えていることがうかがえる。
|
| 2003.06.03 |
|