| > 今週のトピックス > No.712 |
| 直接融資から民間支援機能へ役割を変える住宅金融公庫 | |
| 〜証券化支援スキームによる民間住宅ローンが登場〜 | |
|
● 住宅金融公庫の業務の縮小・見直しのために
小泉内閣による特殊法人改革の一環として、最大の財政投融資(以下、財投)機関である住宅金融公庫(以下、公庫)も業務の縮小・見直しが行われる方向となっている。
平成14年度の「財政投融資資金運用報告」(7月30日財務省発表)によると、公庫では、財投からの借入予定額4兆9,669億円に対する運用残額が4兆8,669億と、約98%に達した。平成14年度の公庫の融資額は約4兆円となっているが、公庫の発表によると、そのほとんどを自己調達で賄うことができたとされている。 公庫の業務縮小に先立つ形で、想定以上に公庫ローンが伸び悩みを見せている背景には、公庫の業務縮小を見越し、民間金融機関が住宅ローン獲得にしのぎを削ったという動きが挙げられる。 例えば、体力のある大手銀行の一部では、「長期・固定金利」という、これまで公庫の独壇場とされた住宅ローン商品を、公庫よりも有利な条件で提供するといったケースもみられた。 ● 地銀や信金での長期・固定金利の住宅ローンが可能になった
このように、自前で公庫に対抗できる住宅ローン商品を提供する金融機関が現れる一方で、相対的に体力の弱い金融機関では、長期・固定金利型の商品は金利リスクが大きく、提供することが困難なのが実情である。
こうした中、10月1日より、公庫の証券化支援事業を活用した民間金融機関の住宅ローンが登場した。この制度により、これまで民間金融機関、とりわけ地方銀行、信用金庫などではリスクが高く、提供することが難しかった最長35年の長期・固定金利型の住宅ローンを提供することが可能になった。 10月16日現在、このスキームに参加している金融機関は、都市銀行2、地方銀行20、第2地方銀行14、信用金庫33、信用組合1、その他3の合計73となっている。 「官から民へ」、また、「民間にできることは民間へ」という時代のすう勢の中で、住宅金融公庫も新たな存在意義を模索していくことになるが、今回のスキームはその一つの例として注目されている。 【証券化支援事業(買取型)のスキーム】
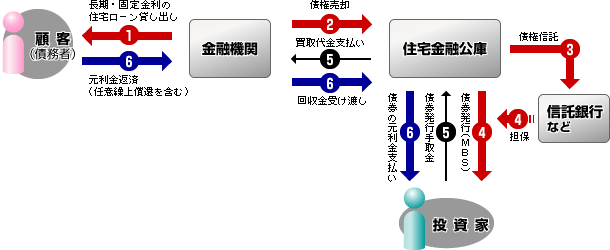 出典:住宅金融公庫ホームページより
|
| 2003.10.27 |
|