| > 今週のトピックス > No.905 |
| 10月1日より確定拠出年金の拠出限度額が引き上げ | |||||||||||||||||
|
● 拠出限度額の引き上げにより役割強化への期待
年金制度改革による公的年金の給付水準の引き下げを補完するための支援として、この10月1日より、確定拠出年金の拠出限度額の引き上げが行われている。具体的な拠出限度額の引き上げ内容は次に示すとおりである。確定拠出年金の掛け金は、企業型では損金算入、個人型では所得控除の対象となるため、拠出限度額の引き上げにより税負担軽減効果が拡大する。公的年金の補完と適格退職年金からの移行を狙って、自分で年金をつくるための自助努力への支援ということになろうが、最大でも月額1万円という引き上げ幅からすると、確定拠出年金への誘導としてはややインパクトが弱いのではないかとも考えられる。そのほか、今年の確定拠出年金の改正では、中途引出しの要件緩和なども行われており、これにより一人でも多くの国民に確定拠出年金の利用価値が認められ、その役割が強化されることに期待したい。また、来年の3月末で凍結期限切れとなる特別法人税についても、厚生労働省や経済産業省、経団連などが来年度の税制改正で廃止を求めており、こちらも動向が気になるところである。
● 確定拠出年金の普及のためには投資教育が課題
確定拠出年金法は、平成13年10月から施行されているが、3年経った今でも確定拠出年金の普及は芳しくない。それでは確定拠出年金のデメリットについてどのように考えているのか。生命保険文化センターが企業側と従業員側について調査した結果をみると次のようになっている。
【図表1 確定拠出のデメリット(企業調査)】
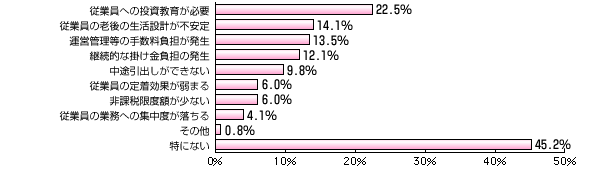 【図表2 確定拠出年金のデメリット(従業員調査)】
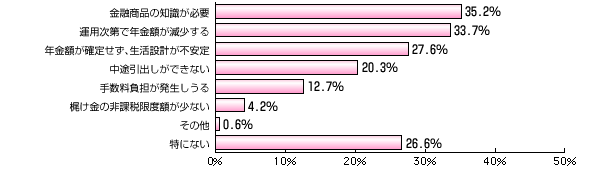 注:複数回答
出典:生命保険文化センター「平成14年度 企業の福利厚生制度に関する調査」
企業側、従業員側のいずれをみても投資に関する教育がネックになっているようである。今回改正された拠出限度額や中途引出しについても問題視されているが、何といっても確定拠出年金ならではの、自己責任にもとづく運用次第で年金額が減少してしまうこともあることへの警戒感が先立つようである。そのためにも投資に関する教育をきっちり受けることが確定拠出年金を普及させるための重要な課題になる。最近よくいわれる"貯蓄から投資へ"という意識改革が国民に根付いていくことに期待したい。
|
| 2004.10.04 |
|