| > 今週のトピックス > No.917 |
| デフレとインフレが並存?“まだら模様”が続く物価情勢 | |
|
● 企業物価指数は上昇傾向に
国内の企業間の出荷・卸売り段階での取引価格を表す国内企業物価指数の上昇傾向が続いている。10月14日に日本銀行が発表した9月の国内企業物価指数(2000年=100、速報値)は96.6と前年同月比(以下同)1.8%上昇と7カ月連続の上昇となり、その伸びは、1991年2月と並ぶ高さになった。
● 素材・原材料は高騰も、最終製品は依然マイナス続く
品目別では、このところの原油や原材料価格の高騰を背景に、石油・石炭製品16.9%、鉄鋼16.0%、非鉄金属14.0%上昇となるなど、素材・原材料、「川上」部門の上昇率の高さが際立っている。一方で、電気機器は4.3%下落となり、最終製品となる「川下」部門では、下げ止まり感はうかがえるものの依然マイナスにとどまっている。
国内企業物価と輸入物価の両方を合計した需要段階別の物価指数動向をみると、「素原材料」は16.6%上昇、「中間財」は4.0%上昇、「最終財」は1.0%下落となった。 ● 「川下」へ波及しづらい状況に
もともと、物価の特性として、「川上」での物価変動が加工段階で企業努力によりある程度吸収されることから、「川下」へ行くほど物価変動が緩やかになる。とはいえ、川上から川下へ、ある程度のタイムラグを持ちつつ、徐々に波及していくのが過去のパターンであった。しかし今回は、川上の上昇が川下に波及しにくい状況にあると指摘されている。
● 消費者物価は依然ゼロ近辺のマイナス
この背景には、個人消費をはじめとする国内需要が、回復傾向にあるとはいえ、決して磐石ではなく、最終消費者に近付くにつれ、価格上昇を転嫁しにくい状況が考えられる。
実際、最終消費者の購入価格の動向を表す消費者物価指数では、一昨年の春ころの1%を超えるマイナスが続いた時期をピークに、最近ではゼロに近いマイナスまで縮小しつつあるが、安定的にプラスに転換する状況にはなく、依然デフレが続いているといえる。 ● 注目が集まる金融政策の行方
こうした物価動向に関連して、日銀では、かねてから「量的緩和」とよばれる現在の"超"金融緩和政策を解除する基準として「消費者物価指数が安定的にゼロ以上になるまで」と公約している。こうした金融政策の行方も絡み、今後の物価動向が注目される。
【図表1 各種物価指数の推移(前年同月比)】
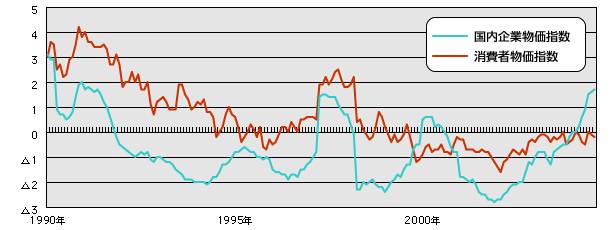 【図表2 需要段階別企業物価指数(前年同月比)】
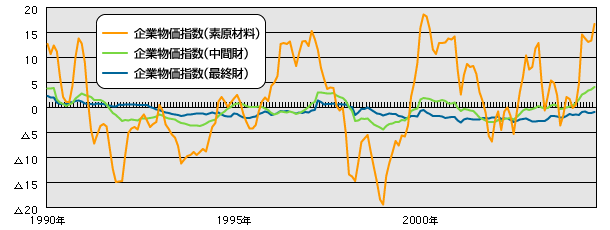 参考:総務省、日本銀行ホームページより
|
| 2004.10.25 |
|