 |

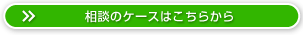 |
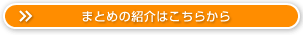 |

 |
|
平成18年度税制改正において、「交際費課税」の基準が明確化されました。税務上「交際費」に該当すると、交際費額の10%が課税(※資本金1億円以下の会社で年間400万円までの交際費について。400万円を超えると一切経費とならない)されますので、節税という観点からはなるべくなら、「交際費」以外の科目で処理したいところです。
今まで交際費に該当するかどうかについては、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」(措置法61条の4)という基準で処理されていました。実務的には、1人当たり3,000円以下の食事代は交際費処理しなくていい、という暗黙のルールもありました。
これが平成18年度税制改正にあたって、「交際飲食費1人当たり5,000円以下については交際費に該当しない」という基準が明示されました。これはありがたい改正といえます。
しかし税務上の交際費から除外されるためには注意点がありますので、まずはそのあたりから解説いたしましょう。
|
|
1つ目の注意点は「金額基準」です。つまり1人当たり5,000円以下という場合の金額基準が、税込みか税抜きかということです。結論は、その会社の経理処理によるということですが、具体的には、税込み経理の場合は「税込みで5,000円以下かどうかを判定するので、5,000円×100/105=4,761円(税抜き、税込み支払い5,000円)」となり、税抜き経理の場合は「税抜きで5,000円以下かどうかを判定するので、5,000円(税抜き、税込み支払い5,250円)」となります。
|
|
改正措置法条文の第3項第2号では、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」に続く括弧書きで、(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)とあります。つまりその飲食費用のうち、支出の相手先が会社内の役員や従業員または身内であるその親族に対するもの(いわゆる社内交際費)は、今回の適用対象から除かれています。これが2つ目の注意点です。
ということは、飲食の相手先の会社名や担当者について、会社内できちんと記録・管理しておくことが必要となります。またこれは、従業員等の不正防止にも役立つことになるのではないでしょうか。
|
|
改正措置法条文の第4項では、「前項第2号の規定(1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費課税から除く)は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する」とあります。つまり、先ほどの飲食における金額基準や相手先について、会社側できちんと該当していることを書類ベースで立証しないといけないことになります。財務省令によると、「日付、飲食先、相手先会社名・担当者名、参加人数、金額など」といった事項を記した書類となります。これをまとめたのが以下の書式で、今後はこのようなツールを使って会社の交際費を管理する必要があります。これが注意の3点目です。
|
| (○○○株式会社 営業第二部) |
| 日付 |
6/15 |
| 飲食先(名称及び住所) |
××居酒屋(東京都新宿区××) |
| 目的 |
乙商品の今後の販売活動支援要請のため |
| 相手先の会社名 |
株式会社△△△ |
| 相手先の担当者 |
販売部 木村徹、高橋進 |
| 当社との関係 |
販売代理店 |
| 自社の担当者 |
営業第二部石井健、建部勉 |
| 参加人数 |
4名 |
| 金額 |
21,000円 |
| 判定(金額÷1.05÷参加人数)≦5,000円 |
○会議費 |
| ※税抜き経理の会社の場合の書式 |
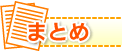 |
経営に活かす術を提案しよう |
|
今回の改正事項を経営的側面で活用できないか、最後に検討してみましょう。
例えば飲食業においては、「1人当たり5,000円以下」に価格設定することは、お客を呼び込むきっかけになるかもしれません。「会議費で処理できる居酒屋」なんていう売り込みも面白いかもしれません。特に大企業や交際費を多く使う中小企業の場合は、会議費などの科目で経費処理できるかどうかによっては、かかった経費の約4割を節税できることになるので影響は大きいといえるでしょう。
私の周囲ではまだこのような打ち出し(1人当たり5,000円以下の居酒屋)を検討している飲食業の方はいないので、税制改正決定後早期に実施することにより、マスコミなどに取り上げてもらえる可能性もあるのではないでしょうか。生き馬の目を抜くような激しい飲食業界ですから、こうした新しい切り口で市場に訴求すれば、思わぬパブリシティ効果があるかもしれません。
こういうアドバイスをコンサルタントという立場からクラインアントに提供してみるのも検討の余地があるのではないでしょうか。
今日の話が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。
|
 |
| 2006.05.22 |
|
 |

 |
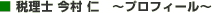
|
[経歴・バックグラウンド]
|
京都府京都市出身
立命館大学経営学部企業会計コース卒
会計事務所を2社経験後、ソニー株式会社に勤務。
その後2003年今村仁税理士事務所を開業、
2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。
|
|
|
[保有資格]
税理士・宅地建物取引主任者・CFP(R)・1級FP技能士など
|
|
 |
|
 |
|