| 事業保険見直し提案のヒント |
|
| |
ヒント 4
役員に「地位と報酬の激変」があった場合には、「実質的に退職したと同様の事情にある」と認められ、支給した退職慰労金が適正額であれば、損金算入が認められます。
<解説>
|
|
| |
法人税基本通達9-2-23(役員の分掌変更等の場合の退職給与)に、この根拠が示されています。 |
| |
・ |
「地位の激変」とは、代表権を持たなくなること
持たないことはもちろん、「実質的にも、その法人の経営上主要な地位を占めていない」と当局から認められることが必要ですから、留意してください。 |
| |
・ |
 「報酬の激変」とは、50%以上減少すること 「報酬の激変」とは、50%以上減少すること
などにより、「実質的に退職したと同様の事情にある」と認められた場合、退職金は損金算入が認められるわけです。 |
|
|
| |
<話法例>
「社長さん、退職金を2度もらいませんか?」
|
|
| |
これは「役員退職金の2回受け取り話法」などと呼ばれているものです。
例えば、社長から監査役や相談役などの非常勤役員になり、実質的にも経営の第一線から手を引いたとき、いわゆる1回目の「みなし退職」のときには老後の生活資金を考えて現金化できる保険種類を、2回目の「完全退職」のときには相続対策を考えて、できるかぎり長期の保険種類の2本立で準備する、という見直し提案が考えられますね。
(注)具体的な提案の際には、税理士等の専門家と相談の上、お取り扱いください。
|
|
|
| |
ヒント 5
死亡退職金は、「500万円×法定相続人数」まで相続税がかかりません。
<解説>
|
|
| |
死亡退職金は法定相続人一人あたり500万円まで非課税です。また、個人で加入している生命保険も、死亡保険金受取人が相続人であれば、同様に一人あたり500万円まで非課税です。そして、これら2つの特典を同時に受けることは、もちろん可能です。 |
|
|
| |
<話法例>
「社長さん、死亡退職金も法定相続人一人につき500万円の非課税枠があることをご存じですか?」
|
|
| |
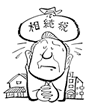 個人で加入の契約で500万円、事業保険で死亡退職金を準備し500万円。
計1,000万円の非課税枠を活用するよう、お勧めする見直し提案が考えられますね。 個人で加入の契約で500万円、事業保険で死亡退職金を準備し500万円。
計1,000万円の非課税枠を活用するよう、お勧めする見直し提案が考えられますね。 |
|
|
| |
ヒント 6
満期になった養老保険の保険金を受け取らず据え置きにしても、満期時に税金がかかります。
<解説>
|
|
| |
こんな例がありました。
ある社長さんが、70歳時に後継者へバトンタッチして引退しようと、そのときの退職金に充当すべく「70歳満期の養老保険」に加入しました。
ところが、70歳になるころには状況が変わり、引退時期を5年ほど遅らせることになりました。
そこで保険金を受け取らず、後継者へバトンタッチする引退時まで据え置くことにしましたが、「発生時点の課税」となり、また、毎年の据え置き利息にも課税されました。 |
|
|
| |
満期時に保険金を受け取り、あらためて保険会社へ預けて据え置きにした、との経理処理が必要だったのですね。
契約時には、引退時期を考慮した、ニーズに合ったプランニングだったわけですが、大変な益金が発生してしまいました。
中小企業の社長さんの場合、「引退時期の予定の変更」は、珍しいことではありません。この場合、養老保険が満期になる前に終身保険へ転換するなどのアフターサービスが必要でしたね。 |
|
|
| |
<話法例>
「社長さん、定年のある保険に加入していませんか?」
|
|
| |
 定年のない社長さんは「辞めるとき=定年退職のとき」ともいえますね。したがって、養老保険(満期=定年のある保険)などから長期平準定期保険や終身保険などへの見直し提案をしてみてください。 定年のない社長さんは「辞めるとき=定年退職のとき」ともいえますね。したがって、養老保険(満期=定年のある保険)などから長期平準定期保険や終身保険などへの見直し提案をしてみてください。 |
|
|
| |
ヒント 7
一般的な贈与と異なり生命保険料については、毎年定期的に定額を贈与した場合でも、一定の要件をクリアしていれば「連年(連続)贈与」と見なされず、毎年の課税となります。
<解説>
|
|
| |
毎年定期的に定額の現金を一定期間贈与した場合には、「連年(連続)贈与」とみなされ、合計金額を一時に贈与したのと同じ税率で課税されます。
しかし、生命保険料については、一定の要件をクリアしていれば「連年(連続)贈与」とみなされないとの根拠は、昭和58年9月に出された国税庁からの「事務連絡」にあります。 |
|
|
|
|
|
| |
実質的に贈与していることを客観的に証明することが必要ですから、①から④の要件ついて、さらに留意点を述べますと、 |
|
| |
①毎年の贈与契約書 |
| |
|
贈与確認のため毎年の贈与契約書を作成します(印紙の貼付は不要)。
※贈与は単年契約のため、毎年贈与契約書が必要です。 |
|
| |
②贈与税申告書 |
| |
|
贈与額が110万円を超える場合は、毎年の贈与税申告書を保管します。 |
|
| |
③生命保険料控除の状況 |
| |
|
契約者は受贈者ですので、贈与者が生命保険料控除を利用することはもちろんできません。 |
|
| |
④その他贈与の事実が確定できるもの |
| |
|
贈与者の口座から受贈者の口座へ保険料を移転し、受贈者の口座から保険料を支払います。
また、受贈者の口座の通帳・印鑑は受贈者が保管することはもちろんです。 |
|
| |
以上の留意点が守られており、贈与を受けていた子ども等(納税者)が「保険料負担者は受贈者である私です」と主張し、当局に認められることが必要です。
ただし、受贈者があまりに幼く、贈与された事実が理解できない場合等、否認される場合がありますので、実行する場合には必ず税理士など専門家に相談してください。 |
|
|
| |
また、贈与に当たって「相続時精算課税制度」を活用するかどうかも、大事なポイントです。「相続時精算課税制度」の詳細については、ここでは省略しますが、
(1)「相続時精算課税制度」を選択する場合
(2)「相続時精算課税制度」は選択せず、上記のような従来からの贈与制度を活用する場合
(3)従来からの贈与制度を数年活用した後「相続時精算課税制度」を選択する場合
などが考えられますが、どのような「贈与」の手法が効果的であるのかは、ケースバイケースですから、上司や先輩によく相談し検討してみてください。 |
|
|
| |
<話法例>
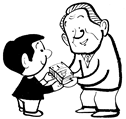 「社長さん、ご自身が保険に入れなくても、生命保険を使った相続対策ができることをご存じですか?」 「社長さん、ご自身が保険に入れなくても、生命保険を使った相続対策ができることをご存じですか?」
加入限度いっぱい、高齢者、健康状態が悪い等の
社長さんや資産家に保険料贈与を使った生命保険加入を
提案してみてください。
|
|
|
| |
ついでにもうひとつヒントを述べさせていただくと、社長さんの保険には医療保険や医療特約をプラスすべきだと思います。反対の考え方もあるでしょうが、私は
社長の病気=会社の病気
と考えます。
特に社長さん一人の影響力が大きい中小企業であればなおさらです。
あくまでも「見舞金」にこだわってしまうと、高額な見舞金は役員賞与として損金不算入となるのでは…、と敬遠されてしまいます。
しかし「見舞金」から「会社を支える資金」へと、使い方・考え方を変えてみてはどうでしょう。売り上げ減少の補てんなど、会社にとって有益な保険金・給付金の活用ができるのではないでしょうか。
|
|
|