機関長と組織長との信頼関係を、また、ひいては所属員と組織長との信頼関係を、破壊しかねない前述のような「バイパス」はナンセンス!
むしろ、組織長の長所や美点を、常日ごろよく観察しよう。そして、機会をみつけて、その長所や美点を所属員に明るくポジティブにPRをし続けよう。組織長と所属員の信頼関係を強めるために。
そうはいっても、「他人の欠点は、すぐ目に付きやすいもの…」、お互いに忍耐強く努力して、「美点凝視」の習慣を、身に付けたいものですね。
それからもうひとつ、「組織長からは、そんなことは言われませんでしたよ…」と所属員。機関長と組織長との間に、所属員育成の仕方(活動とか募集方法・手順、等々)に意見の食い違いがあった場合。その場では言下に否定せず、「うーん、それは組織長に深い考えがあるんだろうね…」等と一応は容認し、後で組織長とよく話し合って調整しよう!
所属員が混乱せず納得するように。
いずれにせよ、
組織長と所属員の信頼を強める「バイパスの努力」。
組織長と所属員との絆を強める「ファスナー」の役目が機関長。
日常のきめ細かな心遣い…、「小事が大事」ですね。その努力の
積み重ねに、組織そして機関を活性化させる「鍵のひとつ」があるのでは…。
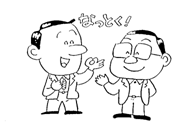
|