あるベテラン機関長が赴任時のあいさつで、「私は『二つのカテイ』を大切にする経営をしたい」と、話を始めました。
一つ目の『カテイ』は、「過程(プロセス)」だ。
成果のみを重視すると、その成果に至る「過程」に目がいかなくなりがちだ。たまたまフロックで得られた、営業力アップを伴わない成果や、怖いのはこの仕事を始めたときに持っていたベースマーケット(イニシャルマーケット)の取り崩しのみで、見込み客が減少していくのを見過ごしてしまい、気付いたときにはもう手遅れ…、なんてことになってしまうことだ。
生保営業は、確かな過程を踏んで収穫を得ていく農作業に似ている。
「見つけ(植え)て」「育てて」「売って(収穫して)」、そして「既契約を守りながらさらに拡大していく」。常に全体のバランスを考えながら、確かな過程を踏んで募集活動を展開していく。そのなかで営業力も鍛えられていくと思う。
荒野を耕して畑を作るのと同じように、生保営業を始めてから既契約の畑を作り上げるまでは大変だ。しかし、作り上げてしまえば、農作業の水やり、草取り、害虫退治などと同じように、しっかりと計画を立てアフターサービス(フォロー)で既契約を守り、そして、機会をとらえて既契約者からの紹介などで、新しい顧客へ拡大していく活動を、堅実におこたらず続けていくならば、長く続けることができる。これが生保営業だと思う。
だから私も、みなさん一人ひとりの成長過程を的確に把握し、助言や同行支援をしていきたい。
二つ目の『カテイ』は、「家庭」だ。
今はFPというけれど、「家庭設計や人生設計」を踏まえた「資産設計」のアドバイザーが生保営業だと思う。だからまず、自分の家庭設計や人生設計をしっかりやろう。社会に開かれた常識豊かな家庭を築いていくことのできる人が、そのまま、生保営業の腕を磨いていくことにもなると思う。
そしてまた、生保営業人として実社会の中で、もまれ鍛えられながら成長していくことが、家庭
人としての成長につながると思うが、どうだろうか。
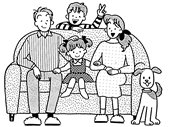
とにかく、家庭を大事に成長してほしい。
そして、「生保営業の仕事をやり続けて本当に良かった」という人生に、一人ひとりがしてほしい。
私も皆さんの成長を、的確に支援できるよう全力で頑張るので、共々に頑張ろう。よろしく!
概ね以上のようなあいさつでした。
機関長駆け出しのころ、ある先輩が教えてくれた…。
「成果への賞賛は、支社でも本社でもできる。一人ひとりの活動内容を日々把握し、成果に現れない営業努力をも認め賞賛できるのは、職員の身近にいる機関長だからだ。
また、一人ひとりのバックグラウンドである家庭を知る努力を怠らないことだ。機関長が見ていてくれる…、知っていてくれる…。それが、職員一人ひとりの向上意欲を高め、成長していく大きな要因になると思う」
との言葉を思い出しながら、共感を持って聞いておりました。
それ以降の、そのベテラン機関長の確かな行動と実績の歩みを見て、さらに共感を深めました。