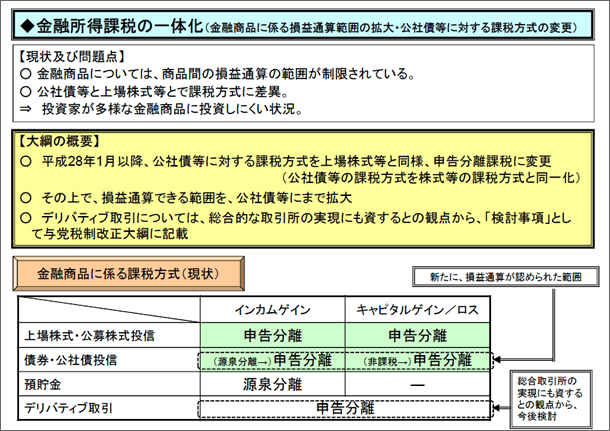|
1 公社債等及び株式等に係る所得に対する課税の見直し
資
医
士
金融所得課税の一体化を進める観点から、公社債等及び株式等に係る所得に対する課税を、次のとおり見直すこととする。
1.特定公社債及び公募公社債投資信託等の受益権の課税方式
特定公社債、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で公募のもの(以下「特定公社債等」)について、次の措置を講ずる。
(1)利子所得等の課税方式等
特定公社債等の利子等については、20%源泉分離課税の対象から除外した上、次の措置を講ずる。
| |
① |
平成28年1月1日以後に居住者等が支払を受けるべき特定公社債等の利子等については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とする。ただし、源泉徴収がされるべき利子等で支払調書の提出等がされないものは、申告分離課税の対象外とする。 |
| |
② |
平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等(源泉徴収(特別徴収)が行われたものに限る)を有する居住者等は、その特定公社債等の利子等については、申告を要しないことができることとする。 |
| |
③ |
居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等で申告分離課税の対象となるものについてその支払の際に課される外国所得税の額がある場合には、その国外公社債等の利子等の額からその外国所得税の額を控除した金額に対して20%(所得税15%、住民税5%)又は15%(所得税のみ)の税率による源泉徴収(特別徴収)を行うこととする。 |
(2)譲渡所得等の課税方式
特定公社債等の譲渡所得等については、非課税の対象から除外した上、次の措置を講ずる。
| |
① |
居住者等が、平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡をした場合には、その特定公社債等の譲渡による譲渡所得等については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とする。
|
| |
② |
特定公社債等の償還又は一部解約等により支払を受ける金額については、これを特定公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とみなすことにより、20%の税率による申告分離課税の対象とするとともに、損失が生じた場合には他の特定公社債等の譲渡所得等から控除することを可能とする。
|
(3)上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰越控除の特例の対象範囲の拡充
| |
① |
上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等を加え、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算を可能とする。
|
| |
② |
平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損失の金額のうち、その年に損益通算をしても控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等からの繰越控除を可能とする。
(注)上記①及び②の上場株式等の配当所得は、申告分離課税を選択したものに限る。
|
| |
③ |
特例の対象となる譲渡の範囲に、公社債を発行した法人が行う買入消却による公社債の譲渡を加える。
|
| |
④ |
確定申告書の提出がなかった場合等の宥恕措置を廃止する。
|
(4)特定口座での取扱い
| |
① |
居住者等が特定口座を開設している金融商品取引業者等への買付けの委託により取得した特定公社債等又はその金融商品取引業者等から取得した特定公社債等を、その特定口座へ受け入れることができることとする。この場合には、特定口座内の特定公社債等に係る譲渡所得等の金額と特定口座以外の特定公社債等に係る譲渡所得等の金額は、区分してこれらの金額を計算することとする。
|
| |
② |
居住者等が金融商品取引業者等の営業所を通じて特定公社債等の利子等の支払を受ける場合において、その居住者等がその金融商品取引業者等の営業所に源泉徴収口座(源泉徴収をする特定口座をいう。以下同じ。)を開設しているときは、その利子等をその源泉徴収口座に受け入れることができることとする。
|
| |
③ |
源泉徴収口座に受け入れた特定公社債等の利子等又は上場株式等の配当等に対する源泉徴収税額(特別徴収税額)を計算する場合において、その源泉徴収口座内における特定公社債等又は上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、その利子等又は配当等の額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して20%(所得税15%、住民税5%)の税率を乗じて徴収すべき所得税及び住民税の額を計算することとする(源泉徴収口座内における損益通算)。
|
| |
④ |
居住者等が平成27年12月31日以前に取得した特定公社債等を、平成28年1月1日に特定口座に受け入れることができる措置を講ずる。また、平成28年1月1日から同年12月31日までの間は、自己が保管する特定公社債等を実際の取得日及び取得価額で特定口座に受け入れることができることとする。
|
(5)特定公社債の範囲
「特定公社債」は、次の公社債(いわゆる金融債で預金保険の対象となっているものを除く。)とする。
| |
① |
国債、地方債、外国国債、外国地方債 |
| |
② |
会社以外の法人が特別の法律により発行する社債(投資法人債及び特定目的会社の特定社債を除く。) |
| |
③ |
公募公社債、上場公社債 |
| |
④ |
発行日の前6カ月以内に有価証券報告書等を提出している法人が発行する社債 |
| |
⑤ |
国外において発行された公社債で、次に掲げるもの(取得後引き続き保護預りがされているものに限る。)
| イ. |
国内において売出しがされたもの |
| ロ. |
国内における私売出しの日前6カ月以内に有価証券報告書等を提出している法人が発行する社債 |
|
| |
⑥ |
金融商品取引所又は外国金融商品取引所において公表されたプログラム(一定の期間内に発行する公社債の上限額、発行者の財務状況等その他その公社債に関する基本的な情報をいう。)に基づき発行される公社債 |
| |
⑦ |
次の外国法人が発行し、又は保証する社債
| イ. |
出資金額等の2分の1以上が外国の政府により出資されている外国法人 |
| ロ. |
外国の特別の法令に基づき設立された外国法人で、その業務がその外国の政府の管理の下で運営されているもの |
|
| |
⑧ |
国際間のとりきめに基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する公社債 |
| |
⑨ |
国内又は国外の法令に基づいて銀行業又は金融商品取引業を行う法人又はその100%子会社等が発行する社債(その取得者が1人又はその関係者のみであるものを除く。) |
| |
⑩ |
平成27年12月31日以前に発行された公社債(発行時に源泉徴収がされた割引債を除く。) |
図 金融所得課税の一体化(金融庁HP「平成25年度税制改正について」P.3)
2.特定公社債以外の公社債及び私募公社債投資信託等の受益権の課税方式
特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の私募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で私募のもの(以下「一般公社債等」)について、次の措置を講ずる。
(1)利子所得等の課税方式
一般公社債等の利子等については、20%源泉分離課税を維持する。ただし、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払を受けるものは、総合課税の対象とする。
(2)譲渡所得等の課税方式
一般公社債等の譲渡所得等については、非課税の対象から除外した上、次の措置を講ずる。
| |
① |
居住者等が、平成28年1月1日以後に一般公社債等の譲渡をした場合には、その一般公社債等の譲渡による譲渡所得等については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とする。
|
| |
② |
一般公社債等の償還又は一部解約等により支払を受ける金額(私募公社債投資信託及び証券投資信託以外の私募投資信託にあっては、信託元本額までに限る。)については、これを一般公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とみなすことにより、20%の税率による申告分離課税の対象とする。ただし、同族会社が発行した社債の償還金でその同族会社の役員等が支払を受けるものは、総合課税の対象とする。
|
3.割引債の課税方式等
割引債を含む公社債の譲渡所得等を課税対象とすることにあわせて、割引債の償還差益についても譲渡所得等として20%(所得税15%、住民税5%)申告分離により課税するとともに、発行時の18%源泉徴収を適用せず、償還時に源泉徴収(特別徴収)をする仕組みとする。具体的には、次のとおりとする。
(1)課税方式
平成28年1月1日以後に行う割引債の償還及び譲渡による所得については、公社債の譲渡所得等として20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とする。ただし、平成27年12月31日以前に発行された割引債でその償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、償還差益に係る18%源泉分離課税を維持し、譲渡による所得は非課税とする。
(2)源泉徴収等
平成28年1月1日以後に発行される割引債については、発行時の18%源泉徴収を適用しないこととする。これに伴い、特定短期公社債(T-Bill・CP)に係る発行時源泉徴収免除の特例は、廃止する。
これに代わり、個人並びに内国法人のうち普通法人等(普通法人並びに法人税法別表に掲げる公共法人、公益法人等及び協同組合等(一般社団・財団法人及び法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人を除く。)をいう。以下同じ。)以外の法人及び外国法人に対して支払う割引債の償還金(発行時に18%源泉徴収がされたものを除く。)については、次のとおり源泉徴収(特別徴収)を行う。
| |
① |
個人に対して支払うもの
国内において平成28年1月1日以後に割引債の償還金(特定口座において支払われるものを除く。)の支払をする者は、その割引債の償還の際、償還金額(支払金額)にみなし割引率を乗じて計算した金額に対して、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収(特別徴収)をし、その徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならないこととする。
| (注) |
源泉徴収口座で管理されている割引債の償還金については、その源泉徴収口座を開設されている金融商品取引業者等が、その割引債の譲渡所得等(償還差益)に対して20%の税率による源泉徴収(特別徴収)を行う。簡易申告口座(源泉徴収をしない特定口座をいう。)で管理されている割引債については、確定申告がされるため源泉徴収(特別徴収)は行わない。 |
|
| |
② |
内国法人で普通法人等以外のもの及び外国法人に対して支払うもの
国内において平成28年1月1日以後に割引債の償還金の支払をする者は、その割引債の償還の際、償還金額(支払金額)にみなし割引率を乗じて計算した金額に対して、15%(所得税のみ)の税率による源泉徴収をし、その徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならないこととする。
ただし、その普通法人等以外の内国法人が、割引債(特定公社債に該当するものに限る。)を管理している金融商品取引業者又は銀行等と取得価額を管理する契約を締結している場合には、実額の償還差益に対して15%の税率による源泉徴収を行うこととする。
| (注 1) |
国内において支払われる特定公社債に該当する割引債の償還金で金融商品取引業者又は銀行等がその支払事務の取扱いをするものは、その金融商品取引業者又は銀行等が上記①及び②の源泉徴収を行うものとする。また、国外において発行された割引債の償還金(国外において支払われるものに限る。)で国内の金融商品取引業者又は銀行等がその支払事務の取扱いをするものも、同様とする。 |
| (注 2) |
非居住者及び外国法人が支払を受けるものについては、一定の要件の下で源泉徴収を行わないこととする。 |
|
(3)みなし割引率
みなし割引率は、次のとおりとする。
①発行日から償還日までの期間が1年以内のもの……0.2%
②発行日から償還日までの期間が1年超のもの………25%
(4)割引債の範囲
その償還金が源泉徴収の対象となる割引債は、次のものとする。
| |
① |
割引の方法により発行された公社債(いわゆる金融債のうち預金保険の対象となっているものを除く。) |
| |
② |
ストリップス債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とを分離してそれぞれ独立して取引されるもの) |
| |
③ |
ディスカウント債(その利子の利率が著しく低い公社債) |
4.株式等に係る譲渡所得等の分離課税の改組
株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得等と非上場株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とした上で、(1)特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税と(2)一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組する。
5.特定管理株式等が価値を失った場合の損失の特例等の拡充
| |
(1) |
特定口座で管理されている内国法人が発行した特定公社債につき、公社債としての価値を失ったことによる損失が生じた場合としてその特定公社債を発行した法人の清算結了等の事実が生じたときは、その事実が生じたことは特定公社債の譲渡をしたこととみなし、かつ、その損失の金額は特定公社債の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とみなして、特定公社債等に係る利子所得等及び上場株式等に係る配当所得との損益通算並びに3年間の繰越控除を可能とする。 |
| |
(2) |
特定管理株式等が価値を失った場合の損失の特例について、本特例によって株式等の譲渡により生じた損失の金額とみなされた金額を上場株式等に係る譲渡損失の金額とみなして、特定公社債等に係る利子所得等及び上場株式等に係る配当所得との損益通算並びに3年間の繰越控除を可能とする。 |
| |
(3) |
特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例について、これらの特例により控除することができる株式の取得に要した金額及び特定株式等の譲渡損失の金額は、特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等並びに一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等から控除できることとする。 |
6.道府県民税利子割及び配当割の見直し
| |
(1) |
平成28年1月1日以後に納税義務者が支払を受けるべき特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外した上、配当割の課税対象とする。 |
| |
(2) |
特定公社債等の利子等について納税義務者が申告した場合には、所得割の課税対象とし、その所得割額からその特定公社債等の利子等に係る配当割額相当額を控除する。 |
| |
(3) |
平成28年1月1日以後に支払われる割引債の償還金(特定口座において支払われるものを除く。)については、その割引債の償還の際、償還金額(支払金額)にみなし割引率を乗じて計算した金額に対して、配当割を課税することとし、その割引債の償還差益については翌年度の所得割の課税対象とし、その所得割額からその割引債の償還金に係る配当割額相当額を控除する。 |
7.道府県民税株式等譲渡所得割の見直し
| |
(1) |
平成28年1月1日以後における源泉徴収口座内の特定公社債等の譲渡所得等については、株式等譲渡所得割の課税対象とする。 |
| |
(2) |
源泉徴収口座内の特定公社債等の譲渡所得等について納税義務者が申告した場合には、所得割の分離課税の対象とし、その所得割額からその特定公社債等の譲渡所得等に係る株式等譲渡所得割相当額を控除する。 |
8.法人に係る利子割の廃止
| |
(1) |
平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者について、利子等の支払を受ける法人を除外し、利子等の支払を受ける個人に限定する。 |
| |
(2) |
法人に係る道府県民税法人税割額から利子割額を控除する制度及びこの制度による控除不足額をその法人に係る道府県民税均等割額等へ充当又は還付する制度を廃止する。 |
|