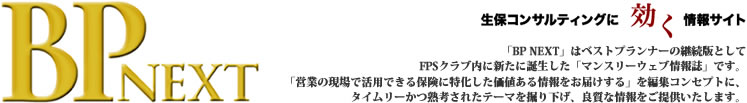生命保険の契約時、保険契約者(または被保険者)は告知書を記入します。告知書を介して商法上の告知義務を果たしているのです。もちろん、これには診査医からの質問に答える口頭告知も含まれます。
生命保険会社が高額死亡保障を中心に販売していたころは、社医や嘱託医による診査が中心だったので、お客さまがあいまいな告知をしても診査医の先生が上手に既往症の病状を聞きだしてくれて、お客さまも正確な病名を思い出し告知することができていたのではないでしょうか。2001年以降の規制緩和による金融の自由化で、死亡保障保険の小口化、生損保による医療保険単品とがん保険の販売など、診査扱いではなく告知書扱いが主流となり、告知書の様式も各社ごとに多様化し現在に至っています。
 ■「自発申告義務」から「質問応答義務」へ
■「自発申告義務」から「質問応答義務」へ

さて、告知書の質問表で聞かれていない事項についてはたとえ悪意または重大な過失による不告知があっても、告知義務違反にはならないと考えられています。しかし商法では、告知をする側には重要事実を自発的に申告する義務があるとされていました。
重要事項とは、
当該契約の締結の可否または契約条件の決定に通常影響をおよぼすと認められる事実をいいます。しかし実際には、具体的に何が重要事実で何がそうでないかをお客さまが自ら判断することは困難です。よって4月1日から施行される保険法では、告知義務に関して「自発申告義務」から「質問応答義務」へと変更されました。つまりお客さまは、告知書に記載された事項についてのみ回答すれば足りることになりました。
これを受け、4月には大部分の保険会社が「限定病名列挙方式」による告知書へ改正すると思われます。この限定病名列挙方式とは、複数の病名が告知書に記されていて、お客さまはその中から自らの現症・既往症に該当するものについて答える方式です。下表はその一例です。
各保険会社の告知書に列挙されている病名は、それぞれ保険会社が重要な疾患と考えているものです。したがってこの質問表に記載されている病気について告知しないことは告知義務違反と見なされることになります。次回からはこの表に記載されている病気を一つずつ取り上げて告知の書き方のポイントを解説していきます。

限定列挙疾患(例)