| > 平成22年度税制改正大綱 ポイントと解説 > 第1章 個人所得課税 |
| 第1章 個人所得課税 | |
|
● 1−4 小規模企業共済及び中小企業退職金共済、中小企業倒産防止共済制度の拡充
小規模企業共済制度は、経営基盤が脆弱で、経済環境の変化を受けやすい小規模企業者の廃業・引退時の生活資金や事業再建資金の確保を図る制度ですが、近年その加入率が減少しています。現行制度の加入対象者は個人事業主のみとなっていますが、家族一体で事業を行われることの多い個人事業の実態を踏まえ、制度改正をし、個人事業主の配偶者や後継者を始めとする共同経営者まで加入対象者を拡大することで、個人事業主の安心を強めることとします。
具体的には、所得税及び個人住民税ともに、小規模企業共済制度の加入対象者に追加される共同経営者について、一定の法律改正を前提に、次の措置を講じます。 1. 共同経営者が支払った掛金については、その全額を所得控除の対象とします。 2. 共同経営者が支給を受ける分割(年金)払いの共済金等については、公的年金等控除を適用し、一括払いの共済金等については退職手当等とみなします。 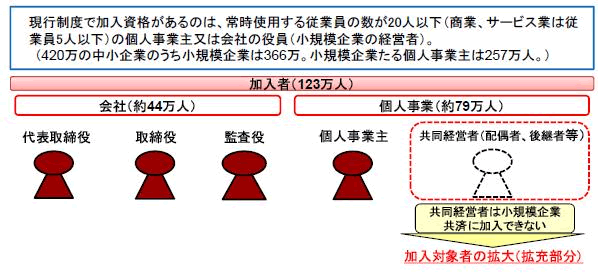 (経済産業省資料より)
また、中小企業退職金共済制度についても、その加入対象者に追加される同居親族のみを雇用する事業の従業員及びその従業員に係る事業主について、所得税及び個人住民税ともに、一定の省令改正を前提に、次の措置を講じます。
1. その事業主掛金については、事業主の所得金額計算上、必要経費に算入します。 2. その掛金に係る従業員の給与所得金額計算上、収入金額に算入しないこととします。 3. その従業員が支給を受ける分割(年金)払いの退職金については公的年金等控除を適用し、一括払いの退職金については退職手当等とみなします。 中小企業退職金共済及び以下の中小企業倒産防止共済制度については、法人税の取扱いも同様となります。 さらには、税制改正項目ではありませんが、経済産業省の税制改正資料には中小企業倒産防止共済制度の拡充も記載されていますので、合わせて記しておきます。中小企業倒産防止共済制度とは、共済契約者が拠出する掛金を原資に、取引先が倒産した際、積み立てた掛金総額の10倍を限度に共済金を無利子・無担保・無保証人で迅速に貸し付け、連鎖倒産を防止するための制度となっています。また、貸し付けを受ける都度、掛金総額から貸付額の10分の1を費用として控除し、掛金は拠出時にその全額の費用処理が認められています。 この度、一定の法律改正を前提に、取引先倒産により回収困難となる売掛金債権の高額化等を踏まえて、貸付限度を現行の3,200万円から8,000万円に引き上げ、これに伴い、費用処理できる掛金限度額を320万円から800万円に引き上げます。 この制度は、単に連鎖倒産防止というだけではなく、節税対策としても有効な制度となっていますので、この拡充による個人事業主及び中小企業への影響は大きいものと思われます。 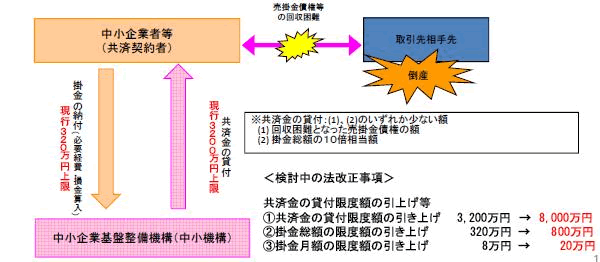 (経済産業省資料より)
|
|