2021年度改定で、介護現場が「実務漬け」!?
2021.01.14
2021年度の介護報酬は+0.7%で決定
2020年12月17日に、厚労省と財務省の間の予算大臣折衝があり、2021年度の介護報酬の改定率が+0.7%と決定した。このうち、新型コロナ感染症に対応するための特例的な評価については、2021年9月末までの間の措置として+0.05%としている。
介護事業者の経営収支は年度ごとに悪化し、加えて新型コロナ禍で利用者減や経費のかかり増しが生じる中、果たして+0.7%という数字でもつのか否か。もちろん、かかり増し経費などに公費による交付金も支給されているが、業界にとって厳しいことに変わりはない。
といって、国民の保険料や利用料負担の増加につながる介護報酬を大幅に引き上げることは、新型コロナ禍によって生活困窮者などが増える中でコンセンサスは得にくい。間もなく団塊世代が75歳以上に差し掛かる時代が来る中で、「報酬増はできる限り抑える」が既定路線とも言えるだろう。問題は、今回の改定率が介護保険を支える現場の負担と折り合いがつくかという点にある。
介護事業者の経営収支は年度ごとに悪化し、加えて新型コロナ禍で利用者減や経費のかかり増しが生じる中、果たして+0.7%という数字でもつのか否か。もちろん、かかり増し経費などに公費による交付金も支給されているが、業界にとって厳しいことに変わりはない。
といって、国民の保険料や利用料負担の増加につながる介護報酬を大幅に引き上げることは、新型コロナ禍によって生活困窮者などが増える中でコンセンサスは得にくい。間もなく団塊世代が75歳以上に差し掛かる時代が来る中で、「報酬増はできる限り抑える」が既定路線とも言えるだろう。問題は、今回の改定率が介護保険を支える現場の負担と折り合いがつくかという点にある。
新型コロナ等で義務づけられる実務が増大
3年に1度となる介護報酬の改定だが、同時に介護サービス事業の運営基準も改定される。つまり、事業所・施設が「何をしなければならないか」という規定を見直すことだ。
こうした運営基準等の改定に向けては、厚労省の社会保障審議会・介護給付費分科会で議論されてきた。そして、その最終的な審議報告が12月23日に示されている(※)。今回の報告を見ると、新型コロナの感染対策をはじめとして、全サービスを通じた「しなければならないこと」が一気に増えている。
たとえば、全サービスを通じて新たに義務づけられた主な内容をざっと上げてみよう。
こうした運営基準等の改定に向けては、厚労省の社会保障審議会・介護給付費分科会で議論されてきた。そして、その最終的な審議報告が12月23日に示されている(※)。今回の報告を見ると、新型コロナの感染対策をはじめとして、全サービスを通じた「しなければならないこと」が一気に増えている。
たとえば、全サービスを通じて新たに義務づけられた主な内容をざっと上げてみよう。
①
感染症対策に向けた項目として、事業所・施設内委員会の開催、指針の整備、研修の実施(ここまでは、施設系サービスではすでに規定済み)、訓練(シミュレーション)の実施
②
感染症や災害発生時の「業務継続」に向けて、計画(BCP)の作成、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施
③
昨今、問題となっている介護現場での高齢者虐待の発生・再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施など
④
認知症対応にかかる従事者の研修受講の状況などを、厚労省が運営する介護サービス情報公表システム上で公表すること
⑤
男女雇用機会均等法等における、介護現場でのハラスメント対策を進めること
現場負担と費用負担のバランスの考え方
①~③については、3年の経過措置が設けられている。とはいえ、新たに委員会を組織したり、指針を整備する、研修や訓練を実施するとなれば、現場従事者(特に管理者等)の実務上の負担もそれなりに増えることは間違いない。委員会開催などは「時間外勤務」となるケースも多く、事業所・施設としては人件費コストも気になるところだ。
もちろん、利用者にしてみれば「安心してサービスを受けるために、これくらいはしてくれなくては」と思う項目も多いだろう。だが、新型コロナの感染拡大下で、重症化しやすい要介護高齢者への感染を防ぐべく感染対策に気が抜けないという中、すでに疲弊している現場スタッフも少なくない。
燃え尽きからの離職によって必要な人員基準が満たせなくなれば、定員を削減する事業所・施設も増えかねない。いざという時の介護の受け皿不足が進行すれば、「高い保険料を払っているのにサービスが使えない」という状況も起こり得る。そのあたりの現場負担と保険料・利用料の負担とのバランスをどう考えるか。介護保険を使う側としても、考え方を整理していくことが必要になりそうだ。
もちろん、利用者にしてみれば「安心してサービスを受けるために、これくらいはしてくれなくては」と思う項目も多いだろう。だが、新型コロナの感染拡大下で、重症化しやすい要介護高齢者への感染を防ぐべく感染対策に気が抜けないという中、すでに疲弊している現場スタッフも少なくない。
燃え尽きからの離職によって必要な人員基準が満たせなくなれば、定員を削減する事業所・施設も増えかねない。いざという時の介護の受け皿不足が進行すれば、「高い保険料を払っているのにサービスが使えない」という状況も起こり得る。そのあたりの現場負担と保険料・利用料の負担とのバランスをどう考えるか。介護保険を使う側としても、考え方を整理していくことが必要になりそうだ。
田中 元(たなか・はじめ)
介護福祉ジャーナリスト。群馬県出身。立教大学法学部卒業後、出版社勤務を経てフリーに。高齢者介護分野を中心に、社会保障制度のあり方を現場視点で検証するというスタンスで取材、執筆活動を展開している。
主な著書に、『2018年度 改正介護保険のポイントがひと目でわかる本』『《全図解》ケアマネ&介護リーダーのための「多職種連携」がうまくいくルールとマナー』(ぱる出版)など多数。
主な著書に、『2018年度 改正介護保険のポイントがひと目でわかる本』『《全図解》ケアマネ&介護リーダーのための「多職種連携」がうまくいくルールとマナー』(ぱる出版)など多数。
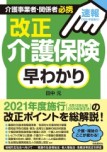
好評発売中!
[速報! 2021年度施行]介護事業者・介護福祉関係者必携!
改正介護保険早わかり(2021年度からの介護保険はこうなる)
改正介護保険早わかり(2021年度からの介護保険はこうなる)
2020・2021年度施行の「改正介護保険」と高齢者福祉・保健・医療関連法のポイントを、いち早く、項目別に詳しく解説。介護、福祉の何が変わるのかが、わかります!
2019年の重要な改正点も収載・解説。
2019年の重要な改正点も収載・解説。








